最近の簿記2級の合格率は低い!
10数年前、簿記2級の合格率は30%前後でした。
ここ数年は、合格率15〜20%と低く、まれに合格率1桁になることもあるくらい難易度が上がっているようです。
実際に受験した人からは「難しかった〜」「やる気を失った〜」という感想がネット上にあげられています。
本記事では、難易度だけでは語れない「簿記2級の合格率がなぜ低いのか」についてお伝えします。
簿記2級の合格率が低い理由を知っていただき、簿記2級合格に向けて頑張るキッカケになれば幸いです。
※本記事は、2022年6月試験までの最新情報でお届けしています。
簿記2級の合格率は年々低くなっている?!

簿記2級の合格率は年々低くなっている?!
そんな声を聴きますが、本当に低くなっているのでしょうか?
まずは、日本商工会議所にて公開されている過去約14年間(121~161回)の簿記2級受験者データをご覧ください。
私が簿記3級を合格した121回(2009年2月22日)、簿記2級を合格した123回(2009回11月15日)の回を含んだ2009年から今までの簿記2級合格率の結果を10回ごとに区切って合格率の平均を出してみました。
それでは、簿記2級の合格率が年々低くなっているかどうかみていきましょう。
| 回 | 受験者数 (申込者数) |
実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 161(2022.6.12) | 16,856名 | 13,118名 | 3,524名 | 26.9% |
| 161回 | 16,856名 | 13,118名 | 3,524名 | 26.9% |
| 回 | 受験者数 (申込者数) |
実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 160(2022.2.27) | 21,974名 | 17,448名 | 3,057名 | 17.5% |
| 159(2021.11.21) | 27,854名 | 22,626名 | 6,932名 | 30.6% |
| 158(2021.6.13) | 28,572名 | 22,711名 | 5,440名 | 24.0% |
| 157(2021.2.28) | 45,173名 | 35,898名 | 3,091名 | 8.6% |
| 156(2020.11.15) | 51,727名 | 39,830名 | 7,255名 | 18.2% |
| 155(2020.6.14) | 中止 | |||
| 154(2020.2.23) | 63,981名 | 46,939名 | 13,409名 | 28.6% |
| 153(2019.11.17) | 62,206名 | 48,744名 | 13,195名 | 27.1% |
| 152(2019.6.9) | 55,702名 | 41,995名 | 10,666名 | 25.4% |
| 151(2019.2.24) | 66,729名 | 49,766名 | 6,297名 | 12.7% |
| 集計 151回~160回 | 423,918名 | 325,957名 | 69,342名 | 21.3% |
| 回 | 受験者数 (申込者数) |
実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 150(2018.11.18) | 64,838名 | 49,516名 | 7,276名 | 14.7% |
| 149(2018.6.10) | 52,694名 | 38,352名 | 5,964名 | 15.6% |
| 148(2018.2.25) | 65,560名 | 48,533名 | 14,384名 | 29.6% |
| 147(2017.11.19) | 63,757名 | 47,917名 | 10,171名 | 21.2% |
| 146(2017.6.11) | 58,359名 | 43,767名 | 20,790名 | 47.5% |
| 145(2017.2.26) | 78,137名 | 60,238名 | 15,075名 | 25.0% |
| 144(2016.11.20) | 72,408名 | 56,530名 | 7,588名 | 13.4% |
| 143(2016.6.12) | 58,198名 | 43,767名 | 11,424名 | 25.8% |
| 142(2016.2.28) | 90,693名 | 70,402名 | 10,421名 | 14.8% |
| 141(2015.11.15) | 76,207名 | 59,801名 | 7,042名 | 11.8% |
| 集計 141回~150回 | 680,851名 | 519,420名 | 110,135名 | 21.2% |
| 回 | 受験者数 (申込者数) |
実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 140(2015.6.14) | 62,473名 | 47,480名 | 16,395名 | 34.5% |
| 139(2015.2.22) | 71,969名 | 55,225名 | 12,054名 | 21.8% |
| 138(2014.11.16) | 70,235名 | 54,188名 | 14,318名 | 26.4% |
| 137(2014.6.8) | 54,773名 | 40,330名 | 13,958名 | 34.6% |
| 136(2014.2.23) | 73,679名 | 55,960名 | 23,254名 | 41.6% |
| 135(2013.11.17) | 77,760名 | 60,377名 | 13,601名 | 22.5% |
| 134(2013.6.9) | 58,206名 | 42,703名 | 5,920名 | 13.9% |
| 133(2013.2.24) | 76,069名 | 57,898名 | 27,538名 | 47.6% |
| 132(2012.11.18) | 79,837名 | 61,796名 | 14,149名 | 22.9% |
| 131(2012.6.10) | 64,353名 | 48,341名 | 14,834名 | 30.7% |
| 集計 131回~140回 | 689,354名 | 524,271名 | 156,021名 | 29.8% |
| 回 | 受験者数 (申込者数) |
実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 130(2012.2.26) | 72,040名 | 53,404名 | 16,808名 | 31.5% |
| 129(2011.11.20) | 83,716名 | 64,052名 | 28,489名 | 44.5% |
| 128(2011.6.12) | 69,890名 | 52,546名 | 18,299名 | 34.8% |
| 127(2011.2.27) | 88,363名 | 66,838名 | 21,653名 | 32.4% |
| 126(2010.11.21) | 90,607名 | 69,100名 | 14,857名 | 21.5% |
| 125(2010.6.13) | 88,621名 | 67,337名 | 26,909名 | 40.0% |
| 124(2010.2.28) | 90,804名 | 66,330名 | 8,244名 | 12.4% |
| 123(2009.11.15) | 97,389名 | 74,371名 | 28,585名 | 38.4% |
| 122(2009.6.14) | 78,645名 | 57,616名 | 14,700名 | 25.5% |
| 121(2009.2.22) | 81,616名 | 60,475名 | 26,053名 | 43.1% |
| 集計 121回~130回 | 841,691名 | 632,069名 | 204,597名 | 32.4% |
【参照】日本商工会議所による過去約14年間(121~161回)の簿記2級受験者データより作成
121回簿記2級から各10回ごとの平均合格率は、121~130回は32.4%、131~140回は29.8%と約30%近くあったものの、150回以降は約20%と年々簿記2級の合格率が低くなっているようです。
161回は26.9%と少し上がっていますが、まだまだこの先はわかりません。
141回~150回(2015.11.15~2018.11.18)の合格率の平均は、21.2%
131回~140回(2012.6.10~2015.6.14)の合格率の平均は、29.8%
121回~130回(2009.2.22~2012.2.26)の合格率の平均は、32.4%
とくに、簿記2級合格率が一番低かった回は157回(2021.2.28)で、合格率たったの8.6%と1桁をはじき出したのは、史上初ではないでしょうか?
下手すると簿記1級の合格率並みの合格率の低さです。
その日のネット上はかなり炎上していました。まだ、記憶が新しいですね。
また、簿記2級合格率が一番高かった回は、133回(2013.2.24)の時で合格率は47.6%です。この差にはものすごく違和感を覚えます。
合格率が一番高い回・・・47.6%(2013.2.24/133回)
それでは、ここまでの簿記2級の合格率を踏まえて、簿記2級の合格率が低い7つの理由をみていきましょう!
難易度だけが問題ではない?簿記2級合格率が低い7つの理由!

なぜこんなにも簿記2級の合格率が低いのでしょうか?
難易度が高い回があるから?
それもないとは言い切れませんが、他にも理由があるのです。
簿記2級の合格率が低い理由は次の7つが考えられます。
一つ一つみていきましょう。
①工業簿記が増えるから
簿記2級合格率が低い理由の1つ目は、「工業簿記が増えるから」です。
簿記3級ではなかった「工業簿記」が試験科目に入ってきます。
「工業簿記」は、企業内部での部門別や製品別の材料・燃料・人力などの資源の投入を記録・計算する技能で、経営管理に必須の知識です。
普段聞きなれない用語も増え、部門別や製品別の計算方法にとまどう方も多いようです。
②商業簿記のレベルがあがるから
簿記2級合格率が低い理由の2つ目は、「商業簿記のレベルがあがるから」です。
簿記3級の試験科目は「商業簿記」のみで、試験問題も基本的な内容でした。しかし、簿記2級になると「商業簿記」は簿記3級のときより試験範囲がぐっと広くなります。
「商業簿記」は、購買活動や販売活動など、企業外部との取引を記録・計算する技能で、企業を取り巻く関係者(経営管理者・取引先・出資者等)に対し、適切、かつ正確な報告(決算書作成)を行うためのものです。
簿記2級の試験問題から、割賦販売などの取引や税効果会計、連結会計など難易度の高い会計処理が試験範囲に加わります。
特に税効果会計や連結会計は実務経験がない人が勉強してもなかなか理解しにくく、商業簿記をさらに難しく感じさせているようです。
③問題数が増えるから
簿記2級合格率が低い理由の3つ目は、「問題数が増えるから」です。
簿記2級では、簿記3級になかった「工業簿記」が増え、「商業簿記」も試験範囲が増えることにより問題数が多くなります。
問題は記述式で解答しなければいけないため、問題を解くのにかかる時間がどうしてもかかってしまいます。
特に、1問1問の問題が簿記3級よりも長いため、どこかで引っかかってしまうと関連した問題に影響が出ることになり、正解率を下げることになります。
④合格できる実力がつくと思って申し込むから
簿記2級合格率が低い理由の4つ目は、「合格できる実力がつくと思って申し込むから」です。
実は、簿記2級の受験申込をして実際に受験した人の割合は75%くらいになります。
受験申込をしたけど実際に受験しなかった人が4人に1人いるということです。
これは、簿記2級の受験日が、2月、6月、11月と1年に3回あるため、勉強期間は「次の試験までに間にあう!」と思い、申し込んだものの、結局勉強が間に合わなかったということです。
勉強が間に合わなかった人の行動としては2パターンあります。
②せっかく申し込んだのだからという勿体ない気持ちから受験される人
簿記2級の試験日までに、勉強が間に合わなかった人が「せっかくだから受けておこう。もしかしたら受かるかもしれない」という気持ちで受験することで、合格率が低くなる要因を作っているのかもしれません。
⑤難易度の低そうな回を予想するから
簿記2級合格率が低い理由の5つ目は、「難易度の低そうな回を予想するから」です。
実は、合格率が高い回の次の回は合格率が下がり、逆に合格率が低い回の次の回は合格率が上がるという流れがあるという話が、数年前にはありました。
おそらく簿記2級の合格率の統計データなどからいろんな方が推測されたのでしょう。
当時はこのように過去の合格率の推移をみて難易度を予想し受験する回を決めていた方がおられたため、実力がつく前に試験を受けるという現象があったのかもしれません。
⑥職場の関係で仕方なく受験する人もいるから
簿記2級合格率が低い理由の6つ目は、「職場命令で仕方なく受験する人もいるから」です。
例えば、税理士事務所に入所、一般企業の経理に配属などにより、簿記2級を取得するよう指示があり、仕事だからと仕方なく受験する人もおられます。
税理士事務所に入所など、もともとそういう仕事をしようとしている場合は頑張れるかもしれません。
しかし、不本意な異動などで配属された場合は、職場で必要な知識だからと簿記2級の受験を指示されてもモチベーションが保てません。
このような理由から簿記2級の合格率が低くなる要因を作っているのだと考えられます。
⑦2016年度から段階的に改定しているから
簿記2級合格率が低い理由の7つ目は、「2016年度から段階的に改定しているから」です。
2016(平成28)年度から段階的に出題内容の改定が行われていました。具体的には、実務での使用頻度が高い内容の追加、実務でほとんど使用しなくなった内容の削除などになります。
当時、事前に出題内容の改定が話題に上がっていたということもあり、大幅な改定前に受験しておこうという人が増えました。
2016(平成28)年度の改定前の合格率が11.8%(141回)、14.8%(142回)と低くなったのは、「改定前に受かるといいな」という記念受験者が少なからずともいたせいではないでしょうか。
改定前の合格率は30%前後ですが、段階的に改定を行うなかで合格率は15〜20%と低い水準になっています。
段階的な改定とはいえ、変化についていくのがキツイと感じられる方もおられるのかもしれません。
もちろん、簿記2級のテキストや講座などでは改定に沿った対策をしてくれていますが、受験者としてみれば心穏やかではないでしょう。
簿記2級の合格率が年々低くなるのは段階的な改定も大きくかかわっているかもしれませんね。
簿記2級合格率が低い理由を克服する方法

ここまでの話から、簿記2級の合格率が低い理由はご理解頂けましたでしょうか?
では、簿記2級の合格率が低い中でも、何とか克服し、合格に導くにはどのようにしたらよいでしょうか?
よく考えてみてください。
日商簿記2級の試験は100点満点です。
合格点は70%以上になります。
70点以上あれば合格できるので、100点満点を取る必要はありません。
工業簿記については簿記2級からはじめて試験範囲となるので、商業簿記よりも難易度が低く、出題パターンもそれほど多くありません。
簿記3級の延長である商業簿記に気を取られるあまり、工業簿記の対策がおろそかになり結果が残せない傾向がみられます。
簿記2級においては商業簿記も工業簿記も完璧を求めるのではなく、全体的に点数を取れるように心がけましょう。
| 試験科目 | 試験時間 | 合格基準 |
| 商業簿記 工業簿記 (原価計算を含む)5題以内 |
90分 (157回までは120分) |
70%以上 |
簿記2級合格率がUP!ネット試験はチャンス倍増?

日商簿記は、2020年12月よりネット試験が導入されました。
今までの統一試験、団体試験(ペーパー試験)にネット試験方式が加わったということです。
ネット試験は、定期的(毎週、毎月)に実施しているネット試験会場もあれば、受験生の希望に応じ随時実施しているネット試験会場があります。
ということは、簿記2級の勉強をして実力がついてきたら、自分の好きな日程で最寄りのネット試験会場を選択すればいいだけなので、ネット試験はチャンスが倍増なのです。
>>簿記のネット試験はいつでも受けられる!統一試験よりチャンス倍増!!

簿記2級合格率が低いのはどっち?ペーパー試験VSネット試験

簿記2級は、統一試験、団体試験(ペーパー試験)、ネット試験方式で実施しております。
試験問題については、3方式いずれも出題範囲や問題の難易度は同じです。
2020年12月開始したネット試験と同時期のペーパー試験の受験者データをみると、ペーパー試験は18.3%、ネット試験の合格率は39.6%とネット試験のほうが合格率が高い結果になります。
ネット試験は試験日が多く、自分の実力がついてきたときに気軽に申し込めるので、年3回しか申し込みできないペーパー試験よりもチャンスも合格率も倍増になるということです。
【統一試験、団体試験(ペーパー試験)】
| 回 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 157(2021.2.28) | 35,898名 | 3,091名 | 8.6% |
| 158(2021.6.13) | 22,711名 | 5,440名 | 24.0% |
| 159(2021.11.21) | 22,626名 | 6,932名 | 30.6% |
| 160(2022.2.27) | 21,974名 | 3,057名 | 17.5% |
| 161(2022.6.12) | 16,856名 | 3,524名 | 26.9% |
| 累計 | 120,065名 | 22,044名 | 18.3% |
【ネット試験】
| 期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2020年12月~2021年3月 | 29,043名 | 13,525名 | 46.6% |
| 2021年4月~2022年3月 | 106,833名 | 40,713名 | 38.1% |
| 2022年4月~2022年6月 | 21,433名 | 8,098名 | 37.8% |
| 累計 | 157,309名 | 62,336名 | 39.6% |
※商工会議所の検定試験「【日商簿記検定試験(2級・3級)ネット試験】受験者データを掲載しました」より作成
簿記2級の勉強方法!独学?通学講座?通信講座?

簿記2級の勉強方法は、独学・通学講座・通信講座の大きく3パターンあります。
独学は勉強時間はかかるが費用が安く、通学講座は同じ目標を持った仲間と頑張れるが費用が高く、通信講座は在宅で勉強できるし費用も抑えられるという、それぞれの特徴があります。
| 勉強方法 | 独学 | 通学講座 | 通信講座 |
| 勉強時間 | 250時間~500時間 (4~8ヶ月) |
150時間~350時間 (2~6ヶ月) |
|
| 合格率(例) (通常15~20%) |
- | 受講者の合格率は90%超という講座も有。 | |
| 費用(例) | 3,000円~ | 80,000円~ | 19,800円~ |
一つ一つみていきましょう。
簿記2級の勉強方法【独学】
簿記2級の勉強方法である「独学」は、とてもシンプルな勉強スタイルです。
自分が見やすい簿記2級のテキストを購入し、自分で勉強計画を立ててすすめていきます。
まず、簿記3級で馴染みのある商業簿記から勉強し、その後初めて見る工業簿記を勉強し、これを3回繰り返して、最後に過去問題集を解くという方法が取り組みやすいでしょう。
テキストも2〜3冊くらいで合格可能なので、簿記2級合格までの費用が一番安く済みます。
>>簿記2級テキストはTAC出版がおすすめ!たった3冊で独学合格できたワケ

簿記2級の勉強方法【通学講座】
簿記2級の勉強方法である「通学講座」は、学生だけでなく、社会人にも人気の勉強スタイルです。
スキルアップのために会社帰りに通ったり、転職などのために会社を退職してから集中して学んだりと自分に合った勉強方法を選択することが可能です。
何より同じ目標を持った仲間とともに学べるので、モチベーションを保ちながら合格まで頑張ることができます。
例:本気になったら大原の「大原学園」など
簿記2級の勉強方法【通信講座】
簿記2級の勉強方法である「通信講座」は、日々忙しくまとまった勉強時間の取りづらい社会人・主婦・学生などの方に向いている勉強スタイルです。
自分の好きな時間にスマホ・PC・タブレットで学べるため、重い資格の本を持ち運ばなくても、通勤時間や休憩時間などのちょっとしたスキマ時間に気軽に勉強をすすめることができます。
例:スキマ時間で簿記を取る!「STUDYing(スタディング)」など
まとめ|簿記2級合格率が低い理由はコレ!自分に合った勉強方法で合格を勝ち取ろう!!

簿記2級の合格率が低いのはなぜでしょうか?
10数年前、簿記2級の合格率は30%前後でした。
ここ数年は、合格率15〜20%と低く、難易度が上がっているようです。
実際に受験した人からは「難しかった〜」「やる気を失った〜」という感想がネット上にあげられています。
しかし、簿記2級の合格率が低い理由は、難易度以外にも次の7つが考えられます。
簿記2級の合格率が低い理由を克服する方法はあるのでしょうか?
日商簿記2級の試験は100点満点です。
合格点は70%以上になります。
70点以上あれば合格できるので、100点満点を取る必要はありません。
簿記2級においては商業簿記も工業簿記も完璧を求めるのではなく、全体的に点数を取れるように心がけるようにしましょう。
簿記2級の合格率は低いですが、ネット試験によるチャンス倍増や、独学・通学講座・通信講座の3つの勉強方法から自分の合った勉強方法を見つけ出し、諦めずに頑張っていきましょう。

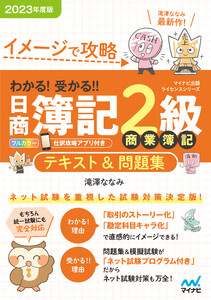
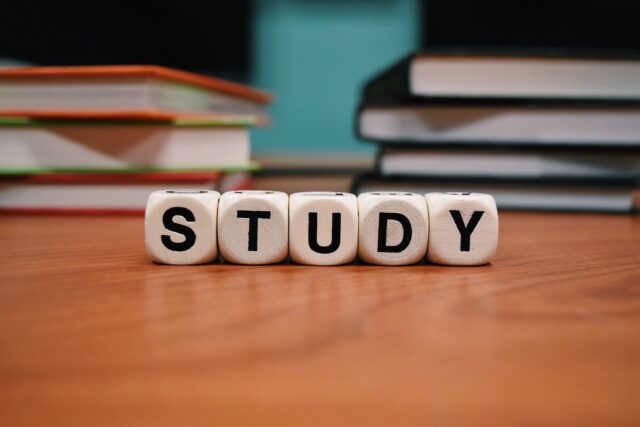

コメント